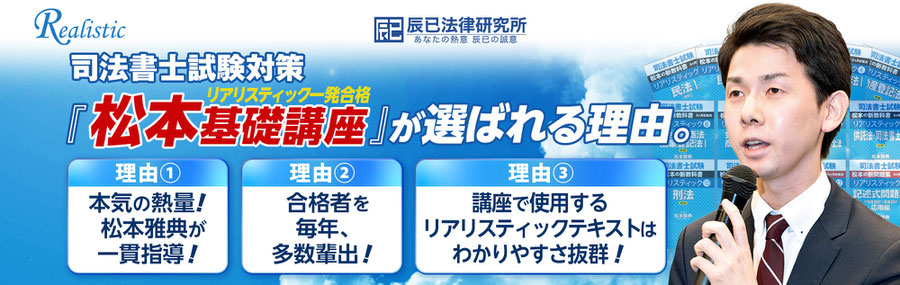リアリスティック民法Ⅰ~Ⅲ
最近の法改正に対応した最新版
★第4版では、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(令和3年4月の物権法、相続法および不動産登記法の改正等。令和5年4月以降順次施行予定。)に対応して必要な改訂を行いました!!
★民法Ⅲ第5版では、2022年12月の民法改正(女性の再婚禁止期間の廃止、嫡出推定制度の見直し等)に対応して必要な改訂を行いました。既に、第4版までに債権法改正・相続法改正、成年年齢改正、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しといった近時の法改正を反映させています。
★民法Ⅲ第6版では、2024年5月に成立した民法改正(父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもの)に対応して必要な改訂を行いました。この改正は、一部の規定を除き2026年5月24日までに施行されます。

第4版 リアリスティック1
民法Ⅰ(総則)
¥2,530(税込)
ページ数: 340ページ
判型: A5
ISBN: 978-4864665933
発売日: 2023/1/20

第4版 リアリスティック2
民法Ⅱ(物権)
¥2,420(税込)
ページ数: 428ページ
判型: A5
ISBN978-4864665544
発売日: 2022/5/14

第5版 リアリスティック3
民法Ⅲ(債権・親族・相続)
令和7年受験向け
¥3,300(税込)
ページ数: 626ページ
判型: A5
ISBN978-4864666046
発売日: 2023/8/30

第6版 リアリスティック3
民法Ⅲ(債権・親族・相続)
令和8年以降受験向け
¥3,520(税込)
ページ数: 656ページ
判型: A5
ISBN978-4864666572
発売日: 2025/2/15
著者・松本雅典講師コメント
司法書士試験講師の松本です。『リアリスティック民法』には,私が講義を行うにあたって考え調べた理由付けや思い出し方を入れられるものはすべて入れました。それは,債権法改正・相続法改正についても同じです。試験当日に勉強してきた知識を思い出すには,「きっかけ」が必要です。そのきっかけとなるのが,理由付けや思い出し方です。これらを武器にして,最短ルートで合格を果たしてください。
多すぎず少なすぎない情報量
自分の知識にできなければ意味がありませんので,掲載する知識は多くしすぎないようにしました。しかし,それで知識不足になってしまっては仕方ないので,少なすぎる情報量でもありません。受験界の中では,情報量は「真ん中」あたりに位置するかと思います。
体系的な学習
法律は「理解」を伴う学習でなければなりません。表面的に知っているだけでなく,「わかる」になっていないと,問題は解けません。「わかる」の語源は「分ける」だといわれています。たとえば,ある知識を示されて,「この知識は代理の要件である顕名のハナシ,この知識は無権代理人の責任追及の要件のハナシ」ということができれば,ほとんど理解できているといっていいでしょう。そこで,体系だった学習ができるように,見出し・小見出しのつけ方にかなり気を配りました。見出し・小見出しは,知識を入れるボックスです。このテキストの見出し・小見出しが,私の頭の中にある民法の知識を入れているボックスであり,みなさんの頭の中に知識の受け皿として作っていただきたいボックスです。
わかりやすい表現
法律は,日常用語と異なる使い方をする用語が多いですし,難しい言い回しも多いです。このテキストでは,初めて法律を学習する方にもわかりやすい表現を心がけました。しかし,これは「正確性」との関係で大変なことでした。わかりやすく言い換えれば,それだけ不正確な表現となってしまうリスクが高くなります。たとえるなら,英語の日本語訳です。英語を日本人にわかりやすく説明したのが日本語訳ですが,日本語に訳す際に意味が変わってしまうリスクがあります。絶対に不正確にならないようにするには,日本語に訳さなければいいのですが,それでは日本語訳になりません。法律も,条文や判例の表現そのままの説明であれば不正確な表現となるリスクはありません。しかし,それは,みなさんがテキストに求めていることではないでしょう。よって,「不正確な表現とならないよう,わかりやすい表現をする」,これに可能な限り挑戦しました。
基本的に「結論」→「理由」の順で記載
書籍は,著者という他人が書いた文章を,著者の助けのない中,自分の頭の中で理解しなければなりません。これは,どんな書籍でも同じです。理解しやすい書籍にするには,著者が自分の自由な順で説明するのではなく,ある程度決まったルールに従うべきです。そこで,説明順序は,基本的に「結論」→「理由」の順としています(説明の都合上,先に理由がきてしまっている箇所も少しあります)。
理由付けを多く記載する
私が毎年講義をする中で調べ,ストックしていった理由付けを,このテキストに記載しました。その数は,相当な数になります。
思い出し方を記載する
知識を記載する前に,「共通する視点」「Realistic rule」「判断基準」などを説明している箇所があります。これらは,“複数の知識を思い出すための思い出し方”です。その他にも,いくつもの思い出し方を記載しています。試験でしなければならないことは,「思い出すこと」だからです。思い出し方まで記載していることに,このテキストの特徴があります。
図を多めに掲載する
民法の法律関係は,図を描いて理解するのが最も有効です。そこで,可能な限り多くの図を掲載しました。
表は適宜掲載する
テキストは,単なる記憶ツールではなく,理解していただくためのツールでもありますので,表を中心に構成してはいません。しかし,比較して記憶したほうが記憶しやすい知識もありますので,そういった箇所は表を適宜掲載しました。